事業計画書とは?意味やメリット、書き方の例をわかりやすく解説
2025-07-04更新
2025/07/04
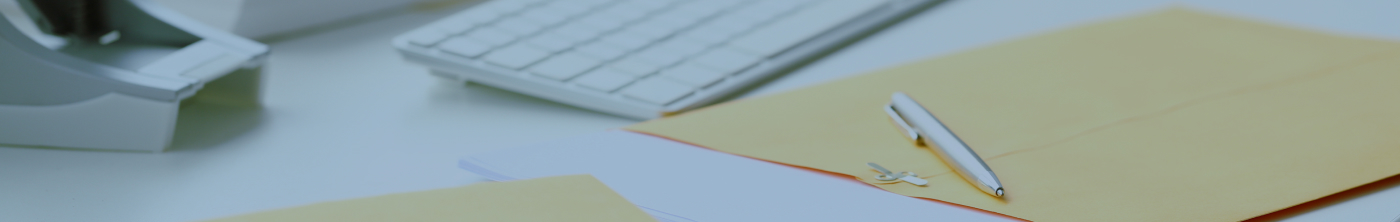
個人事業主やフリーランスの方が融資を受ける際には、事業計画書の作成が求められます。また、事業計画書は融資申請に必要なだけでなく、事業を成功させるための計画を明確にし、実行に移すための重要な行動指針でもあります。
本記事では、事業計画書の役割や作成するメリット、記載項目、書き方の例を解説します。簡単に、かつ効果的に作成するための方法もご紹介します。
事業計画書は、事業の内容や目的、成長戦略、収益の見通しなどを整理して、文章や数値で計画を策定するための書類です。これを作成することにより、自身の事業の強みや収益、支出の見込みを内外に示せます。
しかし、個人事業主やフリーランスの場合、事業計画書を作成したことがない方が多いのが現状です。事業計画書を作成しなくても業務に支障ありませんが、作成することで得られるメリットも多くあります。特に事業を拡大する場合や、事業の方向性に変更がある場合などには作成をおすすめします。
事業者が融資を申し込む際に、金融機関に提出するのが事業計画書です。金融機関が融資を決定する際の判断材料として扱われます。ただし個人事業主やフリーランスの場合、一般的な銀行から融資を受けるのは難しいケースが多いです。そのため、起業前の個人事業主が融資を受けたい場合は、個人事業主向けの融資を提供している日本政策金融公庫への申し込みをおすすめします。その際に必要な書類が「創業計画書」です。
創業計画書は事業計画書の1つですが、創業計画書が起業前または起業直後に作成するのに対し、事業計画書は既に事業を展開している時期に作成するという違いがあります。したがって、個人事業主が開業・起業のために融資を検討している場合は、まずは創業計画書を作成しましょう。
資金調達ナビの「創業計画をつくる」では、日本政策金融公庫の創業融資に必要な創業計画書を解説・ポイントを参考にしながら簡単に作成できます。
事業計画書に決まった作成様式はありません。しかし一般的に記載される項目はあるため、以下で項目や書き方の例をご紹介します。
起業する目的や動機を記載します。目的や動機を明確にすることで、事業の方向性が明らかになり、ステークホルダーへの説得力を高めることが可能です。結果的に融資や支援を受けやすくなります。この項目では、自身にどのような経験があるのか、それを活かして最終的にどのようなことを実現させたいかを記載します。
【フリーランスエンジニアの記入例】
AI技術の進歩により、システム開発の分野では新しい技術が次々と登場している。私は10年間、企業で金融機関向けのシステム開発に従事し、セキュリティ強化や業務効率化に貢献してきた。この実績を活かし、最新の技術を活用したセキュアなシステム開発を提供することで、日本のシステムのデジタル化とセキュリティ向上を支援したい。
【ライターの記入例】
オンラインメディアの台頭に伴い、専門性の高い記事コンテンツの需要が増えている。私はこれまで、SEOやマーケティングを学びながら、企業の広報記事やオウンドメディアの記事作成に携わってきた。この経験を活かし、SEOやマーケティング視点を重視した効果的なコンテンツ制作を行い、企業や個人のブランディングを支援したい。
自身のこれまでの経歴を詳細に記載します。事業に関係する実績があれば積極的に記入して、他に資格やスキルがあれば書きましょう。スキルや実績があれば事業の信頼性を高めることにつながり、融資先が融資を判断する際のプラス材料になります。
【フリーランスエンジニアの記入例】
1.経歴
・〇〇年〇〇株式会社に入社
・〇〇年〇〇プロジェクトにて〇〇の開発に従事
2.資格
・〇〇年ITパスポート試験取得
・〇〇年基本情報技術者試験取得
【ライターの記入例】
1.経歴
・3年間〇〇出版社で編集・ライター業務に従事
・Webメディアにおいて100本以上の執筆
2.スキル・実績
・SEOを意識した記事作成スキル
・SNSマーケティングに関する知識
・ITに関する専門記事の執筆経験
どのような商品・サービスを提供するかを記載する項目です。「飲食店経営」や「エンジニア」といった大枠だけ記載するのではなく、商品・サービスの具体的な内容、提供方法、ターゲット層などを記載します。競合との差別化ポイントや事業の強みを意識して書くことが重要です。
また、補足資料として写真や図を盛り込むと、より詳細な説明ができて効果的です。例えば飲食店を展開する場合、立地や外観、店内のレイアウト、メニュー表などの写真や図があれば、より具体的にイメージを伝えられます。
エンジニアやライターなどの業種では、過去の実績を具体的に示すことで信頼性が高まります。例えば開発したシステムや執筆した記事の実例を資料としてまとめ、提供するサービスの品質や強みを客観的に伝えられると効果的です。
取引先は、どのような相手を想定してサービスを展開するのかを記載する項目です。相手が企業の場合は正式な企業名や業界内のシェアを記載しましょう。特に融資の申し込みで使用する場合は、安定的な取引先であることを示せるため融資判断で有利にはたらく可能性があります。他に、仕入先や販売ルート、外注先、取引の見込みがある企業も記載します。相手が企業ではなく個人であれば「一般個人」のように書きましょう。
また、契約の種類(継続、単発)や支払条件についても記載します。例えば代金の回収方法や支払期日などを具体的に示すことで、事業の安定性や計画の実現性を伝えやすくなります。
借入状況は、事業者個人の借入状況や返済能力を記載する項目です。特に融資審査では借入状況を確認されるため、事前に把握しておきましょう。
具体的には、借入総額や借入先、使い道(住宅や車、教育など)、残高、年間の返済額などを記載します。住宅ローンのような大きな借入があっても、社会的信用の証としてプラスに評価される場合があります。どのような借入があるかを正確に記載することが重要です。
事業運営における収入と支出の予測を記載する項目です。創業から運営後までの状況を想定し、売上目標、売上高、仕入高(売上原価)、経費などを予測し、利益の見込みを算出します。
重要なのは、理想ではなく、現実的な見込みを基に計画を立てることです。例えば販売価格や見込み客数、取引数を試算し、収益構造を具体的に示します。事業開始後に計画と実績がかけ離れた場合はその都度見直し、収支のバランスを調整することが求められます。
従業員の項目は、創業計画書や事業計画書のテンプレートによくある項目です。役員や従業員の人数を記載します。ただし、個人事業主であれば従業員を雇わないことも多いので、その場合は記載する必要はありません。法人でない場合は役員も記載不要です。もし従業員を雇用する場合は従業員の数や内訳(正社員、パートなど)を記載します。
この項目もテンプレートに付属していることが多い項目です。事業に必要なツールの購入資金や運営資金、それを調達する手段を記載します。例えばWebライターとして起業し、個人のWebサイトを作成する場合はサーバー代やドメイン代などが該当します。
調達手段は自己資金、親族や知人からの借入、国からの助成金などがあります。個人事業主やフリーランスの場合は自己資金で対応するケースも多いですが、もし資金調達が必要な場合は、その理由と調達手段を明記します。
事業計画書の作成方法は決まっていないため、書面の様式は自由です。しかし、特に融資を受ける場合は、重要な項目を押さえておく必要があります。
もし自身で作成の仕方がわからない場合は、テンプレートを活用するのが効果的です。重要な項目の抜け漏れを防ぎ、かつ簡単に作成できます。以下のサイトからテンプレートをダウンロードできるので、積極的に活用しましょう。
▼テンプレの種類
日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード」 ![]()
独立行政法人中小企業基盤整備機構「事業計画書の作成例」 ![]()
TOKYO創業ステーション「事業計画書 ダウンロードページ」 ![]()
融資を受けることは事業計画書の重要な目的の一つですが、それ以外にも事業計画書の作成には多くのメリットがあります。
事業の価値を正確に分析するのは容易ではありません。しかし、事業計画書を俯瞰して作成することで、事業の現状や課題を客観視でき、事業の価値と市場のニーズがどのように合致するかを把握できます。
事業計画書を作成することで、売上目標やコスト、利益を数値化でき、具体的な改善策を検討しやすくなります。また、作成の過程で自身の強みや弱みを再認識できるため、今後の事業展開にも役立ちます。数値を明確にすることで現実的な経営戦略を立てられ、計画の実現可能性を高められる点が大きなメリットです。
さらに、事業の進捗を振り返り、改善策を考えるための行動指針としても活用できます。目標を達成できなかったときでも事業計画書があれば当初の考えを振り返ることができ、修正の方向性をスムーズに見つけられます。
事業計画書を作成することで、競合他社との比較分析を行い、自社の強みや弱みを明確にできます。提供する商品やサービスの特徴、価格、ターゲット層などを整理することで、自社ならではの優位性が見えてきます。
また、顧客ニーズと照らし合わせながら競合との差別化ポイントを明確にすることで、競争優位性を確立できます。例えば独自のサービスを強化する、特定の市場で展開するなど、具体的な戦略を打ち出すことが可能です。
こうした差別化ポイントを事業計画書に明記することで、顧客や取引先に対して自社の魅力を効果的にアピールでき、信頼性の向上にもつながります。
事業計画書は、金融機関からの融資だけでなく、新規契約の獲得や取引先拡大にも役立ちます。具体的な事業内容や将来性を明確に示すことで、取引相手の信頼を得やすくなるからです。
また、事業計画書は自社の強みやビジョンを体系的にまとめた資料でもあり、ポートフォリオの発展型としても活用できます。特にIT業界や、イラストレーターのようなクリエイティブな分野では、自身の実績やスキルを補完する資料として有効です。
取引先に対し、具体的な事業計画を提示することで、事業の継続性や成長性を伝え、安心感を与えられます。その結果、契約締結や新たな取引のきっかけにつながる可能性が高まります。
個人事業主やフリーランスは収入が変動しやすいため、資金の管理が重要です。事業計画書を作成し、定期的に見直すことで、最初に立てた目標と実際の資金状況のギャップを把握しやすくなります。
また、資金繰りを把握することで、資金ショートを未然に防ぎ、安定した事業運営につなげることが可能です。事業計画書で収入が落ち込みやすい時期を予測できれば、融資を受けるタイミングを適切に見極め、スムーズな資金調達にも役立ちます。
個人事業主が事業計画書を作成するにはテンプレートを活用するのが有効です。しかしテンプレートをダウンロードしても、自分で記載するのは大変だと感じることがあります。そこで便利なのが、弥生の資金調達ナビ「創業計画をつくる」です。業種に合わせた入力フォームが用意されており、Web上の項目に沿って記入するだけで、具体的な事業計画を無料で作成できます。
個人事業主やフリーランスの方にとって、事業計画書の作成には多くのメリットがあります。事業を立ち上げる前に計画を立てることで、自身の強みや課題、市場のニーズなどを把握し、事業の方向性を明確にできます。たとえ計画通りに進まなくても、設定した目標を見直し、適切に修正できる点も大きな利点です。
また、事業計画書は自身のスキルや事業のリスクを融資先や取引先に示すツールとしても活用できます。融資の申し込みや新規契約の獲得、取引先の拡大にも役立ちます。
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役。早稲田大学理工学部応用化学科卒。都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業。現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行う。

タグ:





